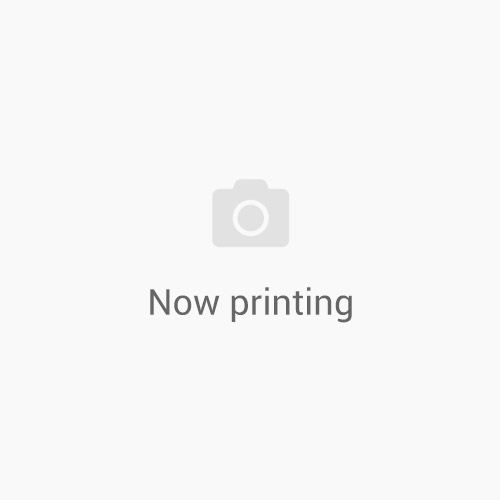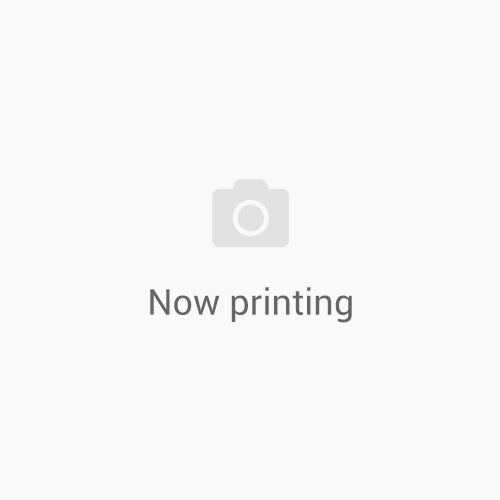サンゴとひとくちに言ってもその種類は多岐に渡り、分類によって飼育方法や飼育難易度にかなりの違いがあります。
この記事では、ソフトコーラル、ハードコーラルといったサンゴの分類についての解説、そして初心者におすすめの種類のサンゴについて解説していきます。
↓2018/01 NEW!! この記事より更に詳しいサンゴの分類や飼育方法に関する記事を書きました。↓

サンゴの分類

サンゴは分類学的には全て刺胞動物門花虫網に属する動物です。
そもそもサンゴとは何かについて簡単にまとめた記事がありますので、サンゴについて何も知らないという方はまず以下の記事から読むと更に理解が深まると思います。

さて、サンゴは全て刺胞動物門花虫網に属する、と言いましたが、更に細かく分類することもでき、この分類によって飼育方法や飼育難易度がかなり違ってきます。
様々な分類の方法がありますが、サンゴ飼育においては、一般的に大きな2つの特徴で分類する事が多いです。
第一に、光合成によりエネルギーを得ているか。
第二に、石灰質の骨格を体の回りに形成するかどうか。です。
これらの組み合わせにより、サンゴは大きく4タイプに分類する事が可能です。それでは、実際にひとつずつ挙げていきましょう。
光合成によりエネルギーを得る、骨格を形成するタイプのサンゴ(造礁性サンゴ)
マリンアクアリウムにおいて、ハードコーラルと呼ばれるタイプのサンゴです。
一般に、サンゴと聞いて想像するような岩のようものはほぼ全てこのカテゴリーのサンゴだと思ってもいいです。
上の画像のサンゴはミドリイシと言うハードコーラルの一種ですが、外見からして骨格を形成しているのがよくわかります。
おさらいになりますが、このサンゴの骨格部分はサンゴ本体ではなく、実際のサンゴ本体はこの骨格の中に住む無数の触手(ポリプ)ひとつひとつです。
ミドリイシはとても小さなポリプが無数に集まってできた群体性サンゴと言う事ですね。
繰り返しになりますが、ポリプや群体性サンゴについては以下の記事で詳しく解説していますので、まだ読んでいないという方はぜひ読んでみてください。

また、上記の画像のサンゴはナガレハナサンゴと言うハードコーラルの一種ですが、こちらはミドリイシとは違い、明らかに柔らかそうな触手(ポリプ)が目立ち、骨格を形成しているというのが分かりづらくなっています。
しかし実際にはこの触手(ポリプ)の根元部分に骨格があり、そこにこの大きなポリプが住んでいます。
ナガレハナサンゴなどの一部のハードコーラルは、ポリプが骨格に比べてあまりに大きい為、ポリプで骨格が見えなくなり、骨格が存在しないように見えてしまいます。逆にミドリイシなどのハードコーラルは、ポリプが骨格に比べてあまりに小さい為、骨格がサンゴ本体であるように見えてしまいます。
ミドリイシのように、骨格に比べポリプが非常に小さいハードコーラルをSPSと言います。
ハードコーラルの中に更に分類があって、その1つがSPSという感じです。ちなみにSPSはSmall Polyp Stony Coralの略で、これは小さなポリプの石サンゴという意味です。
そして、ナガレハナサンゴのように、骨格に比べポリプが非常に大きいハードコーラルをLPSと言います。
LPSはLarge Polyp Stony Coralの略で、これは大きなポリプの石サンゴという意味です。特徴の通りですので覚えやすいですね。
さて、ハードコーラルを更に分類することでみなさんの頭がこんがらがってしまっているところでしょうが、この分類をしたことには理由があります。
それは、SPSとLPSでは飼育方法や難易度にかなり違いがあるからです。
まず、SPSについて説明しますが、SPSは、サンゴ本体であるポリプに比べ、非常に大きな骨格を形成する必要があるため、多くのエネルギーを必要とします。
すなわち、多く光合成をしてもらう必要があり、よって多くの太陽光エネルギーを必要とします。
従って、飼育する場合も同様に、強力な照明を当てる必要があります。
また、水質の変化・悪化にも弱い為、水質を高レベルで維持する為の特別なろ過装置などが必要となります。
一方、LPSはサンゴ本体であるポリプに比べ骨格はそこまで大きくないので、SPSに比べるとそこまで強力な光を必要としません。
実際、LPSはSPSに比べて深い場所に生息している事が多いようです。
また、理由は定かではありませんが、SPSに比べてLPSの方が水質の変化・悪化に強く、より簡素な飼育設備でも飼育が可能です。
このように、SPSとLPSでは飼育方法や飼育難易度に大きく違いがあるため、同じハードコーラルという分類ではありますが、飼育に関しては全く別のものと考えてください。
言うまでもなく、飼育難易度としてはSPS>LPSですので、初心者の方がハードコーラルを飼育する場合は、まずはLPSから飼育する事を強くおすすめします。
SPS、LPSの詳しい飼育方法や必要な機材については以下の記事でまとめてあります。


また、実際によく飼育される人気のハードコーラル一覧については以下の記事でまとめてありますので参考にしてください。

光合成によりエネルギーを得るが、骨格は持たないタイプのサンゴ(軟質サンゴ)
マリンアクアリウムにおいて、一般にソフトコーラルと呼ばれるサンゴです。
骨格は持たないと言っていますが、実際にはこれは誤りで、体内に細かな骨片をいくつも持っています。
ですが、外見はとても柔らかそうで、骨格を持たないように見えるので、ここでは(ポリプの外側に)骨格を持たないサンゴとします。
ソフトコーラルの特徴としては、やはり柔らかそうなポリプを持つということが挙げられるでしょう。
このサンゴはスジチヂミトサカというソフトコーラルの一種ですが、明らかに柔らかそうな見た目をしていて、実際に触っても、ふにゃっと曲がってしまうくらい柔らかいです。
飼育という観点から見たソフトコーラルの特徴としては、飼育難易度が低い種類が多い、と言う点がそうでしょう。
多くのソフトコーラルが、強力な光を必要とせず、また、水質の変化・悪化にも強いので、飼育難易度としては非常に低いと言えます。
マメスナギンチャクやスターポリプといったソフトコーラルは、海水魚を飼育するような設備でも飼育する事ができ、飼育難易度の低い初心者向けのサンゴの代表です。
以上のようなことからソフトコーラルは、サンゴ飼育初心者にもおすすめできる、サンゴ飼育上達の登竜門的存在だと言えます。
ただし、一部のソフトコーラル(ウミアザミなど)は、SPS並に飼育条件が難しかったりするので、こういった例外もあることは知っておきましょう。
ソフトコーラルの詳しい飼育方法や必要な機材については以下の記事でまとめてあります。

また、実際によく飼育される人気のソフトコーラル一覧とその飼育方法については以下の記事でまとめてありますので参考にしてください。

光合成によりエネルギーを得ない、骨格を持つタイプのサンゴ(陰日性ハードコーラル)
陰日性サンゴと呼ばれるもののうち、骨格を形成するタイプのサンゴです。上記の画像のキサンゴなどが有名です。
陰日性サンゴとは、光合成によりエネルギーを得ない、すなわち褐虫藻を体内に持たず、ほぼ100%捕食によってエネルギーを得ているサンゴです。
光合成をしない、すなわち光を必要としないので、基本的には光の届かない深い場所に生息しています。
また、捕食が生命線となるので、ポリプはプランクトンなどの餌を捕らえやすいように大型化しているのも特徴と言えます。
このタイプのサンゴは、総じて飼育難易度が非常に高いことでも有名です。
飼育難易度が高い理由としては、まずほぼ100%捕食に依存しているので、サンゴへの給餌が欠かせないという点です。
この給餌というのが厄介で、ほぼ毎日ポリプひとつひとつにピンセットやスポイトを使って丁寧に乾燥エビやプランクトンフードなどの餌を与える必要があります。
加えて、この餌やりで水質が悪化するのが非常に早いため、高頻度での水換えなども欠かせません。
また、元来深い場所に生息している種ですので、水温はそれを再現した低め(20℃~22℃程度)にする必要があり、また光が当たるのを嫌うこともあるのでこういったことにも配慮しなくてはいけません。
一言で言うと、飼育に非常に手間が掛かるサンゴだということです(笑)
これらの性質から、基本的には陰日性サンゴのみを飼育する専用水槽で飼育することがほとんどです。
この専用水槽は、水温や水質悪化の関係で、他のソフトコーラルやハードコーラルや、ほとんどの海水魚を一緒に飼育することは難しいです。
ですので、このタイプのサンゴはよほど強く飼育したいという思いがない限りは、趣味の範囲での飼育は現実的では無い気がします。
ただ、ベテランの方で専用水槽を立ち上げ、長期間維持されている方もいますので、飼育自体が不可能と言う訳ではありません。
ですが、初心者におすすめできるかと言われると・・・「絶対におすすめしない」と言い切れるレベルで飼育が難しく、手間の掛かるタイプのサンゴです。
光合成によりエネルギーを得ず、骨格も持たないタイプのサンゴ(陰日性ソフトコーラル)
陰日性サンゴと呼ばれるもののうち、骨格を形成しないタイプのサンゴです。
このタイプのサンゴの中では、上記の画像のような、ヤギと呼ばれるサンゴが有名です。
飼育方法や難易度は上記の陰日性ハードコーラルに準じますので割愛します。
加えると、陰日性ソフトコーラルの方がポリプが小型のものが多く、すなわち給餌が困難な種が多いので陰日性ハードコーラルよりも更に飼育難易度は高いと言えます。
ヤギ類を長期間安定して飼育するのは、ベテランの方でも非常に困難であると言えます。
もはやここまで飼育難易度が高いと、「切り花」のように短い期間だけ見て楽しむという飼育方法になってしまうことがほとんどでしょう。
筆者も数回飼育を試みましたが、やはり数ヶ月で死なせてしまいました。
飼育難易度としては、趣味のレベルでの海水生物ではウミウシに並ぶ難易度だと思います・・・。
飼育はよほどのチャレンジャーでない限りは避けたほうが無難だと思います。
まとめ
サンゴの種類・分類についてできるだけわかりやすく解説したつもりですがどうでしたか?
解説を踏まえて、飼育難易度としては
陰日性ソフトコーラル>陰日性ハードコーラル>SPS>LPS>ソフトコーラル
という感じになります。もちろん、初心者におすすめできる順番としては逆になります。
ソフトコーラルは飼育が非常に簡単で、初心者の方でも海水魚が飼育できる程度の設備さえあれば、誰でも簡単に飼う事ができると思います。
LPSは若干クセがありますが、それでも飼育は比較的容易で、そこまで高価な機材も要求しないのでソフトコーラルからのステップアップにおすすめだと言えます。
SPSは高価な機材、大型の水槽、高い飼育スキルを要求しますので、初心者の方がはじめに飼育するサンゴとしてはおすすめできません。ですが、SPSには他のサンゴにはない魅力がたくさんありますので、他のサンゴで経験を積んだ後に、是非挑戦していただきたいです。
実際、サンゴを飼育していくと最終的にSPSの飼育に行き着くことが多いです。多くのベテランの方が、SPSの飼育をメインに行っていると思います。
陰日性サンゴは総じて飼育難易度が高いので、初心者の方は飼育は諦めるのが無難でしょう。
決して簡単な趣味ではありませんが、サンゴ飼育は非常に奥深い趣味です。
海水魚を飼育しているのでしたら、是非サンゴ飼育にも挑戦してみてはいかがでしょうか?
ただし、サンゴも生き物であり、近年は各地でサンゴの絶滅などが囁かれています。ですのでサンゴを飼育するならば、責任を持ってきちんと下調べをし、飼育環境を整え、絶対に死なせないという気持ちで飼育に臨むようにしましょう。
これらサンゴの飼育方法については以下の記事で詳しく解説していますのでこの記事を読んだ後におすすめです。

また、具体的な初心者におすすめのサンゴについては以下の記事で詳しく解説しています。